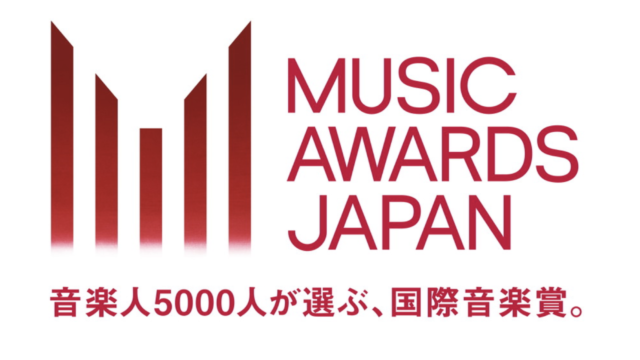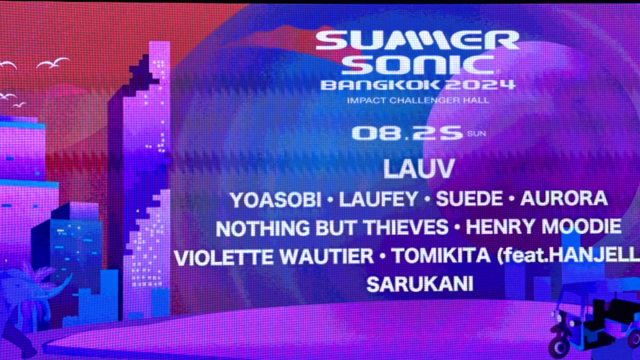JO1が海外の大型フェスに初出演するなら、私は迷わず「ロラパルーザ(Lollapalooza)」を推したい。そう考えるのは、フェス自体の性質、開催場所の利便性、観客層の幅広さ、そして何よりJO1の音楽性との親和性の高さにある。この記事では、なぜロラパルーザがJO1にとって理想的な初海外フェスの舞台なのかを、さまざまな観点から論じていきたい。
ロラパルーザとは?
ロラパルーザは、1991年にJane’s Addictionのボーカル、ペリー・ファレルが立ち上げた音楽フェスティバルだ。当初はツアー型フェスとしてアメリカやカナダを巡っていたが、2005年以降はイリノイ州シカゴのグラント・パークで毎年開催される定着型フェスへと進化した。
ロラパルーザの最大の魅力は、そのジャンルの多様性にある。オルタナティブロック、ヒップホップ、EDM、ポップ、さらにはK-POPやラテンなど、グローバルな音楽シーンを映し出すラインナップが特徴だ。近年ではBLACKPINK(2019)、J-Hope(2022)、NewJeans(2023)、Stray Kids(2023)など、K-POP勢が出演し話題となった。こうした傾向は、非英語圏アーティストが国境を越えて観客を魅了する場として、ロラパルーザが進化している証でもある。
また、ロラパルーザはアメリカだけでなく、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ドイツ、インドなどでも開催されており、真のグローバルフェスと呼ぶにふさわしい存在だ。開催都市ごとにローカル色もありつつ、共通して“多様性”と“開かれた音楽体験”を重視している点が、他のフェスと一線を画す。
都市型フェスという利点
シカゴのダウンタウンにあるグラント・パークで行われるロラパルーザは、都市型フェスの代表格だ。郊外で開催されるフェスとは異なり、公共交通機関で簡単にアクセスでき、周辺にはホテルや飲食店が豊富に存在する。滞在と移動のストレスが少ないため、初めて海外フェスに足を運ぶ人や、短期滞在の海外旅行者にとって非常に参加しやすい。
また、開催時期は7月末〜8月初旬と、アメリカの学生や会社員が比較的休暇を取りやすい夏のバケーションシーズンと重なる。この点も、観客動員のしやすさという意味で非常に大きい。日本から渡航するファンにとっても、3泊4日〜4泊5日でのスケジュールを組みやすく、週末を挟んで行けるという点でも現実的だ。
コーチェラのように郊外型で宿泊環境に制限があったり、移動に車が必須だったりするフェスとは対照的に、ロラパルーザは“気軽に行ける国際フェス”という位置づけが可能だ。
JO1との親和性
JO1はダンスパフォーマンスとボーカルを高次元で融合させたJ-POPグループでありながら、ビジュアル、コンセプト、グローバル意識の高さなど、世界基準でも通用する強みを持つ。特に、曲ごとの世界観構築力や、ステージ演出へのこだわりは、ロラパルーザのような多様な観客が集まる場で際立つ可能性が高い。
JO1の音楽性には、「J-POPらしさ」と「K-POP的完成度」が絶妙に混ざり合っている部分がある。彼らの音楽は、ストリーミングやSNSを通じて海外でもすでに一定の認知があり、その上でライブ・パフォーマンスによって“真価が伝わる”という性質を持つ。ロラパルーザのような開かれたフェスでは、観客にとって新しい音楽との出会いが重視されるため、JO1のように“聴いて初めて魅力に気づく”タイプのグループは非常に相性が良い。
海外展開とタイミングの妙
これまでJO1は、KCONや単独ライブ、SNS上の展開を通じて海外ファン層を徐々に拡大してきた。特に2024年のニューヨーク公演ではチケットが完売するなど、地道な努力の成果が着実に現れている。だが、次のステップに進むためには、“文化イベント”や“プロモーション”の枠を超え、一般音楽リスナーの目に触れる場=本格的な音楽フェス出演が欠かせない。
その点で、ロラパルーザは格別だ。ファンダムに支えられた動員ではなく、会場に偶然いた観客の心を掴むことができるかどうか。これは今後JO1が本当にグローバルに展開する上でのリトマス試験紙のようなものだ。そして、その結果はファンだけでなく、音楽メディアや業界関係者、次のコラボレーター候補にも届いていく。
ロラパルーザが持つ国際的な広がり
ロラパルーザはアメリカのみならず、南米(アルゼンチン、ブラジル、チリ)やヨーロッパ(ドイツ、フランス)、さらにはインドにも進出している。このネットワークは、単発の出演に留まらず、継続的な海外展開を見据えた“ルート開拓”にもつながる。
たとえば、JO1がシカゴでのロラパルーザに出演した後、翌年にロラパルーザ・ブラジルやドイツへ招致されるというような展開も十分に想定できる。その際、地域ごとのファンベースや受容度を見ながら戦略的にマーケットを広げていける。これは、K-POPが過去10年以上かけて積み上げてきたモデルと似た構造を、J-POPグループが初めてトレースできるチャンスでもある。
出演後に起こる波及効果
仮にJO1がロラパルーザに出演した場合、その影響は一過性の話題にとどまらない。まず国内メディアが大きく報じ、ファン以外の層にも「海外フェス出演」という実績が届く。そしてSNSでは世界中の観客の“発見ツイート”や現地映像が拡散され、J-POPに興味のなかった音楽ファンにも届いていく。
また、Apple MusicやSpotifyのプレイリスト、YouTubeのアルゴリズムにも変化が出る。つまり、出演は単なるライブ機会ではなく、グローバルな音楽経済圏に乗る第一歩でもある。ライブの質はもちろん、その後の配信やプロモーションにおける加速度も計算に入れたとき、ロラパルーザはまさに“ハブ”のような存在だ。
コーチェラとの比較と初出演としての最適性
しばしば「海外フェス」といえば真っ先に挙がるのがコーチェラだが、こと“初出演”という観点で見ると、必ずしも最適とは言い切れない。
コーチェラはカリフォルニア州インディオという砂漠地帯の郊外で開催される。アクセスの悪さに加え、チケットは宿泊込みで高額になることが多く、初参加のアーティストにとっても、初参戦のファンにとっても敷居は高めだ。また、コーチェラはライフスタイル重視の側面が強く、ファッション、インフルエンサー文化、ソーシャルメディア映えなどが重要視される傾向もある。
もちろん、アーティストとしてコーチェラに立てるのは大きな名誉だが、初めて海外の観客の前に立つ場としては、ステージの規模や構成、観客との距離感、フェス全体の雰囲気などを総合的に考えると、ロラパルーザの方が「音楽性そのもので勝負できる環境」と言える。
まとめ
JO1が海外フェスに初出演するなら、ロラパルーザ以上にふさわしい舞台はないだろう。都市型でアクセスが良く、参加ハードルが低く、音楽ジャンルに対する寛容さと多様性を持ち、アイドルや非英語圏アーティストも積極的に迎え入れているこのフェスは、まさに「世界への第一歩」にふさわしい。
JO1がそのステージに立つ日を想像するだけでワクワクする。彼らの持つエンターテインメント力が、ロラパルーザという巨大な音楽の器でどう輝くのか。その日を楽しみに、これからも応援を続けたい。